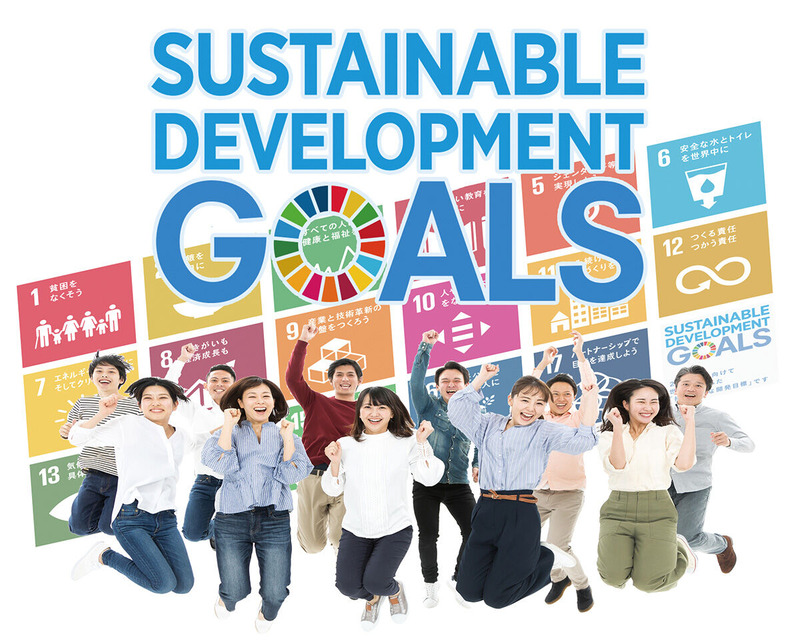
国連が2030年までに実現をめざす「持続可能な開発目標(SDGs)」。達成期限までの残り10年を見据え、政府は昨年12月20日、中長期的な国家戦略である「SDGs実施指針」を初めて改定しました。
■目標まで残り10年、議会の政策提案が重要に
SDGsは、貧困、教育、エネルギー、気候変動といった17の目標からなり、全ての国連加盟国が共有する国際目標です。政府は今回、国内外での進捗状況も踏まえ、16年12月に策定した実施指針を改定。今後4年でより本格的な行動を加速・拡大する方針です。
SDGsの改定指針は、今後4年の中長期的な行動方針となるもので非常に重要です。
とりわけ、8分野の優先課題には、ジェンダー平等の実現や、気候変動対策が掲げられています。いずれも対応に遅れが見られると指摘されており、今後の具体的な行動が極めて重要です。
また、多様なステークホルダーの役割として、「議会」が初めて盛り込まれたことも注目すべきです。「誰一人取り残さない」社会をめざすSDGs達成のためには、地方自治体や地域社会での活動が最重要となっています。
■改定指針のポイント
- ジェンダー平等の実現や、防災、気候変動対策などを優先課題に
- 目標達成へ幅広いステークホルダー(利害関係者)と協働
- 若者への教育・啓発を強化
- 社会課題の解決へ議会の政策提案を期待
- 国際行事を生かし、日本のSDGsモデルの発信と国内での主流化を推進
■地方自治体の役割(SDGs実施指針改訂版より)
国内において「誰一人取り残されない」社会を実現するためには、広く日本全国にSDGsを浸透させる必要がある。そのためには、地方自治体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組が不可欠であり、一層の浸透・主流化を図ることが期待される。
現在、日本国内の地域においては、人口減少、地域経済の縮小等の課題を抱えており、地方自治体におけるSDGs達成へ向けた取組は、まさにこうした地域課題の解決に資するものであり、SDGsを原動力とした地方創生を推進することが期待されている。
地方自治体は、SDGs達成へ向けた取組をさらに加速化させるとともに、各地域の優良事例を国内外に一層積極的に発信、共有していくことが期待されている。具体的には、「SDGs日本モデル」宣言や「SDGs全国フォーラム」等のように、全国の地方自治体が自発的にSDGsを原動力とした地方創生を主導する旨の宣言等を行うとともに、国際的・全国的なイベントを開催する等により、海外や、全国又は地域ブロック、若しくは共通の地域課題解決を目指す地方自治体間等での連携がなされ、相互の取組の共有等により、より一層、SDGs達成へ向けた取組が行われることが期待される。また、今後は、より多くの地方自治体において、更なるSDGsの浸透を目指し、多様なステークホルダーに対してアプローチすることが期待されている。
地方自治体においては、体制づくりとして、部局を横断する推進組織の設置、執行体制の整備を推進すること、各種計画への反映として、様々な計画にSDGsの要素を反映すること、進捗を管理するガバナンス手法を確立すること、情報発信と成果の共有として、SDGsの取組を的確に測定すること、さらに、国内外を問わないステークホルダーとの連携を推進すること、ローカル指標の設定等を行うことが期待されている。また、地域レベルの官、民、マルチステークホルダー連携の枠組の構築等を通じて、官民連携による地域課題の解決を一層推進させることが期待されている。さらに、「地方創生SDGs金融」を通じた自律的好循環を形成するために、地域事業者等を対象にした登録・認証制度の構築等を目指すことが期待されている。地方自治体においては、各地域のエネルギー、自然資源や都市基盤、産業集積等に加えて、文化、風土、組織・コミュニティなど様々な地域資源を活用し、持続可能な社会を形成する「地域循環共生圏」の創造に取り組む等、自治体における多様で独自のSDGsの実施を推進することが期待されている。


