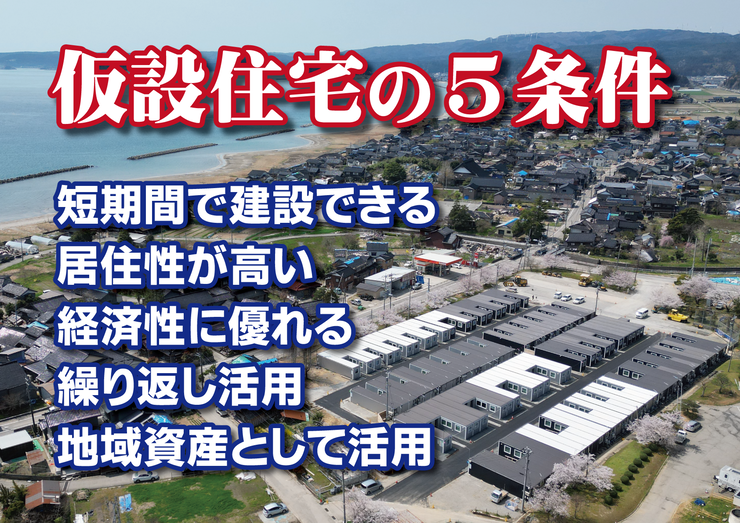2025年4月16日、日立の大煙突周辺のオオシマザクラが満開となり、ドローンでの空撮を行いました。
日立鉱山の煙害で荒廃した山々の緑を取り戻すため、大煙突が完成した大正4年(1915年)以降、日立の山々には大規模な植林が行われました。煙害に強いオオシマザクラなど、約500万本が植えられました。
このオオシマザクラの大群落は、人工のものとしては日本最大と言われています。世界一の大煙突を作り煙害を克服し、オオシマザクラを植林し自然を回復させた。大煙突とさくらに日立の誇りの歴史があります。

日立は日本最大のオオシマザクラの人工群落
今年も4月中旬を迎え、日立市の大煙突周辺には淡いピンク色のオオシマザクラが優しく春の訪れを告げています。日立のオオシマザクラは自生したものではなく、人の手で植林されたものです。
植林のきっかけをつくったのは、日立鉱山の地所係の鏑木徳二と山村次一でした。伊豆大島の火山噴煙地帯で硫黄分の多い土地に自生するオオシマザクラの種子や苗木を取り寄せ、日立鉱山の荒廃地へ次々と植え込んでいきました。しかし、苗木育成は試行錯誤の連続でした。種子は乾燥に弱く、ほとんどが発芽せず苦心したところ、3年目に偶然にも堆肥置場の下部で発芽したものを発見。これを大切に育てることで、大正4年(1915年)には良質な苗木を大量に収穫できるようになりました。
こうして育まれた苗木は、荒廃地の崩壊防止や山肌の再生を目的に、昭和7年(1932年)までの約20年間で260万本ものオオシマザクラが植えられました。さらに日立鉱山は市内外の希望者へも無償で苗木を配布し、昭和12年(1937年)までに72万本を超える配布実績を誇ります。無料配布と自社植林を合わせると、日立周辺には1,000万本以上の桜の苗木が根づき、緑豊かな風景が広がりました。
オオシマザクラの苗木がうまく育つようになると農事試験場の担当者は、この苗木にソメイヨシノの苗を接ぎ木して桜の苗木を多量につくり出しました。当時の日立鉱山の工場長・角弥太郎はこの花の美しさに着目して大正6年(1917)の頃に社宅、道路、鉱山電車沿いに約2000本を植えさせました。これが日立市の春を彩るソメイヨシノのルーツといわれています。
日立市役所の西側の高台(旧日本鉱業諏訪台社宅跡地)の一角に桜塚と刻まれている石碑があり、そこには「大正六年春 角弥太郎氏 諏訪台に櫻樹を植う 昭和九年四月十日」と記されています。
こうした取り組みは、当時の煙害問題に対する日立鉱山の真摯な姿勢と、地域の未来を見据えた壮大な植林プロジェクトでした。明治から昭和にかけて続いた植林活動は、現在でも日立の山々や街路に息づき、春になると市民の目を楽しませてくれます。
(この原稿は、「大煙突とさくら100年プロジェクト」発行の「大煙突とさくらのまち読本」を参考にしました。)