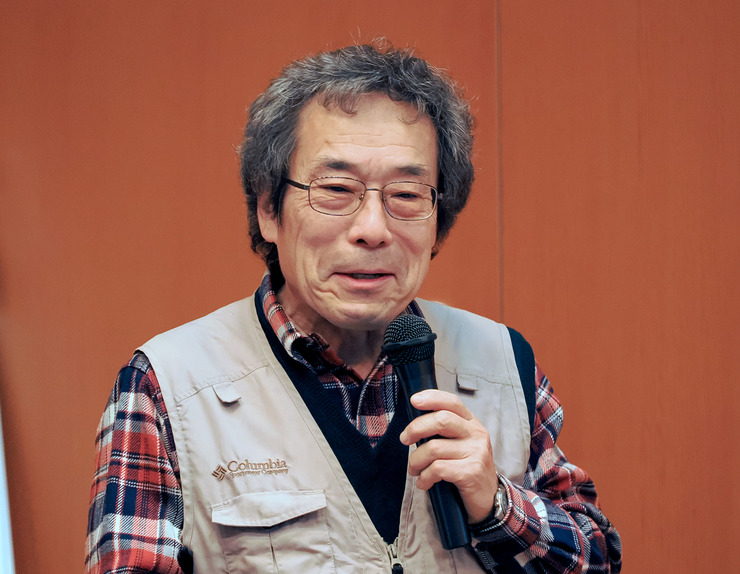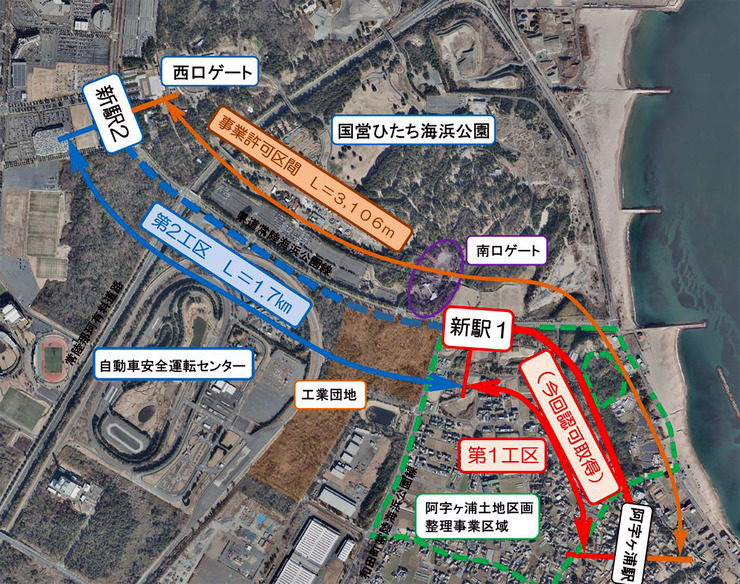11月9日に開催された茨城大学名誉教授の安藤寿男先生の講演会の模様を、youtubeにアップしました。安藤先生が、北茨城の五浦の魅力を古代の歴史に遡って熱く語っています。
50分近くありますが、ぜひご視聴ください。
日時:2024年11月9日
会場:天心記念五浦美術館
主催:NPOいばらきTU・NA・GUジオ
後援:茨城大学、茨城県、北茨城市、(一社)地方創生戦略研究所
令和6年度茨城県企業連携型NPO支援事業
動画撮影・制作:(一社)地方創生戦略研究所

11月9日、NPO法人いばらきTU・NA・GUジオ主催の講演会「天心が愛した五浦の自然」が、天心記念五浦美術館講堂で開催されました。
講師は茨城大学名誉教授の安藤寿男先生。NHKのブラタモリにも、解説者として出演した経歴があります。
北茨城市五浦海岸には奇岩奇礁が広がり、近代日本美術の発展に多大な功績を残した岡倉天心の旧宅や庭園があることから、国の登録記念物(名勝地・遺跡関係)に指定されています。五浦海岸周辺の奇岩奇礁は、世界最大級の炭酸塩コンクリーションからなる硬い塊状や層状の堆積岩からできています。炭酸塩コンクリーションは化石や砂粒などを核として、その周りに珪酸や炭酸塩などの成分が高濃度で集まり、砂などと一緒に固まったものです。 名前のように、まさにコンクリートのように硬く、別名ノジュールとも呼ばれます。五浦海岸にその炭酸塩コンクリーションが形成されだしたのは約1650万年前と計算されています。ユーラシア大陸から日本列島が分離して日本海が拡大していた時代に対応し、日本海の拡大と日本列島の移動を伴う地殻変動によって海底下深部の油ガス田に亀裂が生じ湧出した天然ガスによって出来上がりました。

安藤教授ら茨城大学と北海道大学の研究チームは、2020年、五浦海岸周辺に広く分布している炭酸塩コンクリーションから多数の試料を採取し、野外観察や光学顕微鏡観察によって試料の特徴を明らかにしました。この分析結果から、炭酸塩コンクリーションを構成するほとんどの炭素が、地下深部の熱によって生成した天然ガスに由来していることが明らかにしました。
現存する五浦炭酸塩コンクリーションを形成する炭酸塩の体積は少なくとも600万m3以上あります。この炭酸塩炭素のほとんどが天然ガスに由来しており、約73億m3以上のメタンガスが変化して形成されたものです。風化侵食によって既に消失した炭酸塩が大量にあるので、実際にはさらに多くの炭酸塩コンクリーションが形成されており、また、海底に湧出した天然ガスの一部だけが炭酸塩を形成するので、実際に油ガス田から流失した天然ガス量は73億m3よりもはるかに大量であったと考えられます。
これは五浦地域に巨大ガス田に匹敵する大規模な油ガス田が存在していたことを示しています。このように長期間にわたる天然ガスの海底湧出によって形成された大規模な炭酸塩コンクリーションはこれまで報告されておらず、五浦炭酸塩コンクリーションは世界最大級のものです。幻の「五浦油ガス田」は日本ではこれまで知られていなかった新しいタイプです。